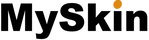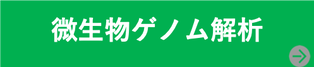弊社では、微生物を対象とした遺伝子解析サービスを行っています。
製品評価や研究開発をご検討のお客様は、ぜひ弊社サービスをご利用ください。
製品評価や研究開発をご検討のお客様は、ぜひ弊社サービスをご利用ください。
独自の微生物採取キットMySkin®キットを使用することにより、簡単に微生物叢を採取することができます。
メタゲノム解析をはじめとして、サンプル中に含まれる微生物DNA量(コピー数)も測定することが可能です。
常に変動する微生物の状態をより正確に把握し、そのデータを個人に適合した製品開発に役立てていただきたいと考えています。
メタゲノム解析をはじめとして、サンプル中に含まれる微生物DNA量(コピー数)も測定することが可能です。
常に変動する微生物の状態をより正確に把握し、そのデータを個人に適合した製品開発に役立てていただきたいと考えています。
微生物を対象としたゲノム解析サービスを提供しております。
細菌のスクリーニング後の遺伝子解析や比較ゲノム解析、パンゲノム解析をはじめとした様々な研究にお役立て下さい。
細菌のスクリーニング後の遺伝子解析や比較ゲノム解析、パンゲノム解析をはじめとした様々な研究にお役立て下さい。